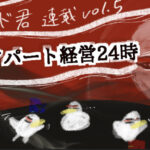作家・伊坂幸太郎さんが執筆する「死神」シリーズのカバー写真や、カメラ専門誌「月刊カメラマン」の表紙を一年間手がけるなど、多方面で活躍する写真家の藤里一郎さん。そんな藤里さんの、写真家人生25周年の集大成ともなる写真集「Intangible」が10月25日に発売されました。
写真集の発売に合わせ、写真展「Intangible」を10月25日(月)~10月31日(日)に東京・Nine Galleryで開催されます。
今回の写真集は藤里さんの新たな挑戦が込められた内容に仕上がっています。被写体を務めたセクシー女優の夏目響さんと共に、藤里さんの写真集・写真展への想いや、作品作りを通して感じた葛藤や苦労を伺いました。
被写体の夏目さんに伝えたのは「気配と匂いと温度の3つを写したい」それだけ
−写真集「Intangible」のモデルはどのような過程を経て、夏目さんに決まったのでしょうか?
藤里:以前写真展のモデルをお願いした広瀬りおなさんのデビュー作に、夏目さんも出演していて、すごく印象に残っていたんです。だけどその作品に夏目さんは無記名で出演していたので、名前は把握できていなかった。その後メーカーの方と企画を考える場でいただいた、いくつかの宣材の中に夏目さんの宣材があり、「あの人だ」と。それで、すぐに撮影の依頼をしたんです。
−撮影をするにあたり藤里さんは夏目さんに、写真集のテーマやコンセプトをどのように伝えたのでしょうか?
藤里:今回の新作は今までとは違った作品にしたいという想いもあって、あえて事細かにコンセプトを決めなかったんです。だから夏目さんには「気配と匂いと温度の3つを写したい」それだけを伝えました。
夏目:その話を受けて、どうやったらそれが実現できるのか一ヶ月毎日考えたんです。でも振り返ると、やっぱり難しかったですね。
−かなりの時間をかけて向き合ったんですね?
夏目:私自身が完璧にやろうとしすぎて残りの体力がなくなるとか、目の前にあることに一生懸命になりすぎる性格だということもあるんだと思います。決して完璧な人間なんかじゃないけど、日常でも「もっとこうしたらいいのに」という気持ちが湧いてくることも多くて。それが欠点でもあるんですが。
藤里:もちろん、夏目さんは頭もいいしサービス精神も旺盛なので、こちらが指示すればその通りにポーズを作ってくれることはわかってたんです。でも、今回の写真集に関しては僕の心象風景の中に夏目さんがただ存在していてほしかった。だから、何もしないでそこにいてほしいというお願いになってしまったんです。
出来上がった写真に嵐の前のような静けさを感じた

−撮影において、意識した点を教えてください。
藤里:写真集はデジタルとフィルムで撮影した写真が混在しているんです。枠が付いてる写真は二眼レフカメラで撮った写真。縦でも横でもない、『真四角』っていうサイズにこだわっていて。

−そのサイズ感にこだわった理由は?
藤里:そもそも写真って、無限にある世界を四隅で切り取るのものですよね。このサイズは奥行きや広がりが出づらいので、逆に自分の世界観が出やすいんですよ。ごまかしがきかない。それに、トリミングをせずに写真を使うので、レンズをどう覗くのか、シャッターをどう切るのかという一つひとつの作業に責任がかかってくるんです。
−出来上がった写真を見ていかがでしたか?
藤里:こんな気持ちになるのは初めてだったんですけど、現像が上がってきた写真を見て、いつもだったらすぐに「いいじゃん」ってなるんだけど、今回はならなかったんですよ。ただ、嵐の前の静けさのような感覚があった。試しに信頼するアートディレクターに見せてみたら、良い悪いは言わないんだけど「すごいね」って返ってきて。それで手応えを感じました。

−特に印象に残っている一枚は?
藤里:この写真をプリントしたときは「この先、このポートレートを越えられなくてもいい」と思いました。この写真がまさに自分の中の集大成だと思ったし、ちょっともうポートレートを撮らなくなってもいいかな、とすら思いました。それはいまだに思ってますよ。
葛藤を隠し通した撮影現場に、自身の精神が残されているような感覚

−夏目さんは自身の写真を見ていかがでしたか?
夏目:撮影が終わって3ヶ月ほど経つんですが、実はまだ勇気がなくて全部見れてないんです。いい写真になったことは分かってるんですけど、でも撮影した3日間のいろんな感情がギュって入って、全部乗ってるから、まだそれに向き合えてない自分がいます。
−そういった感情になることは過去の撮影現場でもあるんでしょうか?
夏目:これが初めてです。撮影の日までだいぶ考え込んだんですよ。撮影が始まっても「本当にこれでいいのか」って悩みながら、時間が経つにつれてその感情が膨らんでいって、ついにはこの場から失踪したいという気持ちにまでなって。撮影後2週間くらいはまだ家にいる感覚がなかった。体は帰ってきたけど、気持ちはまだ撮られていた場所にあるというか。
−そんな夏目さんの心境を藤里さんは把握していましたか?
藤里:知らなかったです。夏目さんに書いてもらった写真集のあとがきを読んで初めて知った。それに、撮影前の一ヶ月すべてを今回の撮影の準備に費やしてくれた、というのもあとがきで知って衝撃でしたね。
−撮影では戸惑いや不安を出さずに被写体を務めていたんですね。
夏目:そうですね。隠し通せていたと思います。ただ、本当はもっとうまくやれると思ってました。自分なりに真剣に考えて意気込んで準備してきたけど、追い詰められるばかりで。それは藤里さんにではなくて、自分自身に。藤里さんは終始ニコニコして楽しそうに撮影されてたんだけど。
藤里:いつもみたいにファインダーを凝視してたら、心情の変化みたいなものは感じていたのかもしれないけど、今回はファインダーを意識的に凝視せず撮影していたからかもしれないですね。僕自身、写真に全てが写りすぎて見えすぎることに飽き飽きしていたから、今回はピントを合わせるという行為をまず排除したんですよ。そうじゃないと気配とか匂いとか温度が写らないと思って。
誰が撮ったとか誰が写ってるとか関係なく、そこにあるものを感じて欲しい

−夏目さんのあとがき拝読しました。これは藤里さんが夏目さんに依頼を?
藤里:はい。夏目さんの少し狂気を感じる文章が魅力的で好きなんですよ。普段文章を読むのって苦手なんですけど、珍しく夏目さんの文章は読めるんですよね。
−鮮烈な吐露とも取れる文章でした。
夏目:出だしだけ少し書けたんですけど、そこから書けなかったんです。藤里さんにも、印刷待ってくれている人にも、手に取ってくれる人にも申し訳ないと思ったけど、どうしても書けなかった。書けなくて悔し泣きしました。それで、撮影の少し前から記録していたスマホのメモを代わりに貼って補いました。
藤里:これを読んで、もしかして「撮らなかった方が良かったのかな」って一瞬よぎったんだけど、でもやっぱり理屈じゃなく誰が撮って誰が写ってるっていうこと関係なしに何かそこにあるものを感じてほしいと思った。
夏目:あとがきでは「もう二度と嫌だ」みたいなことを書いてるんですけど、でもそれは今回の撮影がインタラクティブな撮影だから、プレッシャーを感じていたからであって。この先は、また全然違う作品を一緒に作れたらなと思っています。この撮影があったからこそ、動画の作品に関わるときもより良いものにしたい、という気持ちが強くなりましたね。
藤里:僕も、夏目さんからこれからまた新たにスタートを切るきっかけを逆に与えてもらいました。

−最後に今回の作品作りを振り返ってみていかがでしたか?
夏目:まだ写真が見れていないのは、この撮影を終わりにしたくないからっていう気持ちもあるんだと思います。自分の中ではまだ完結していない。
藤里:僕自身もまだ撮り足りてはいませんね。そういう意味ではこの作品は一向に完結しないと思います。
藤里一郎と夏目響が作り出した未完結の傑作
被写体として魂を削った夏目さんと、作品に対峙した際に畏怖のような気持ちを持った藤里さん。撮影現場では互いに異なる感情を抱いていたものの、現在は共通して作品の引力に気付いている二人。まるで作品が写真の枠を超えて、二人を飲み込む現象のように変化しているようでした。ぜひ、そんな作品を実際に目にして、心揺さぶる体験をしてみてはいかがでしょうか。
プロフィール▼
藤里一郎
1969年生まれ。
男っぷりのよい写真、色香あふれる写真を撮る当世一“Hip”な写真家。
東京工芸大学短期大学部卒業後、大倉舜二氏に師事、96年独立。
以降フリーランス。
アーティスト“May J.”のコンサートツアー・オフィシャルフォトグラファーとして活動するほか、人気作家・“伊坂幸太郎”の「死神」シリーズのカバー写真をてがける。
2018年度、カメラ雑誌「月刊カメラマン」40周年記念年の表紙を1年間担当し、また、2017~2018にかけてラジオパーソナリティとしての経験も持つ。
書籍として日本写真企画刊「ポートレイトノススメ」も出版している。
夏目響
2020年2月発売の作品への特典付録DVDでプレデビュー。
出演者名表記は「名前はまだない。」と匿名での作品出演。
同年5月1日に芸名が「夏目響」と発表。5月21日に「夏目響」の正式デビュー作としてDVD&Blu-rayで同時発売。
月刊FANZA発表「このAV女優がすごい!2020夏」新人部門3位獲得
現在はAV女優の他、モデル業など多岐に渡り活動をしている。
インタビュアー:5歳 ライティング:いちじく舞