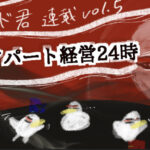「あそこなんだか作りそこねた落とし穴みたいなところじゃない?」
村上春樹の小説「ノルウェイの森」でそんな風に表現された町、北海道旭川市。私はその旭川市で小学校から大学まで過ごした。盆地のため、夏は暑く冬はバカみたいに寒い町。周囲を山々に囲まれた地形は、確かに落とし穴を連想させる。
そんな旭川市出身の大物ミュージシャンと言えば、玉置浩二である。ロックバンド・安全地帯のメンバーであり、類稀な歌唱力でソロミュージシャンとしても活躍するボーカリスト、玉置浩二。そんな化け物シンガーと、カラオケでジュディマリを歌ったら彼氏に途中で停止ボタンを押された暗い過去を持つ私が、同じ町で同じ正油ラーメンを食べて育ったとは、俄かには信じ難い話である。
さて、私は大学生の頃、スポーツジムで受付のアルバイトをしていた。この町で大学生のアルバイトといえば飲食店が大半であったが、根っからの怠け者である私は動き回ったり物を運んだりすることをどうにか回避したく思い、シゴトガイド(北海道の一部地域で絶大なシェアを誇る求人情報誌)を毎月購入しては、出来る限り動かずに済みそうなバイトを血眼になって探した。楽をするためなら決して時間と手間を惜しまない、怠け者界一の努力家である。
そんな努力の末に見つけたスポーツジムの受付は、予想通りほとんど動き回る必要がない上に、運動している人々を眺めているだけで自分も何となく健康になったような気になれる大変お得なアルバイトであった。ただ、向上心を持つ者たちが集うスポーツジムという空間で私のような自堕落人間は異質な匂いを放っていたらしく、それを嗅ぎつけたムキムキマッチョな店長に「お前は目が死んでいる!」「チャレンジしろ!」「やればできる!」と叱咤激励され、遂には15分間延々と腹筋をしまくるレッスンを任されることになってしまい泣きながら腹筋を鍛える羽目になったりもしたが、その15分間以外は事務的な仕事が大半だったため、どうにかこうにか続けることができていたのであった。
そんなある日のことである。大学にて、いつものように眠気との戦いにあっさりと敗北し、つむじで講義を聞いていたところ、勤務中のバイト仲間から一通のメールが届いた。
「玉置浩二と青田典子が来てる!」
一瞬で目が覚めた。その頃の玉置浩二と青田典子といえば、交際が発覚して電撃結婚したばかりという、世間で話題沸騰中のカップルであった。バイト仲間によると二人は入会しに来たわけではなく、ビジターでランニングマシンなどを利用している真っ最中だという。玉置浩二の生まれ故郷に帰省か何かでやって来て、スポーツジムを探してたまたま入店したのが私のバイト先だった、ということだろうか。
なんにせよ、緊急事態である。この町でプライベートの芸能人にばったり会える機会など滅多にあることではない。しかも今話題のアベックである。会いたい。絶対に会いたい。当時ミーハーに見られることを何より恐れ、湘南乃風と一定の距離を保つべくカラオケでおしぼりを回すときも極力無表情でレゲエ砂浜Big Wave!!するよう心掛けていた私であるが、玉置浩二と青田典子がアベックで登場となれば話は別である。なりふり構ってなどいられない。私は講義が終わると同時に駐輪場へとダッシュした。本当は次のコマも講義が入っていたのだが、迷うことなくサボった。それどころではないのである。
急いで自転車に跨り、バイト先へと向かった。河川の多い旭川には橋も多く、大きな橋は坂が長くてきつい。玉置浩二と青田典子に会いたい、その一心で坂道を立ち漕ぎした。生きて、いくんだ、それで、いいんだ、と重いペダルを片足ずつ踏み締めながら進む。頭の中で、麦わら帽子を被った玉置浩二がギターをかき鳴らし、私を鼓舞する。からのミルクビンにタンポポさすあいつも、タンポポをさしたからのミルクビンを掲げながら応援してくれている。僕がいるんだ、みんないるんだ、バイト先に玉置浩二と青田典子がいるんだ!
息を切らしてバイト先に辿り着き、入り口の扉を開けた。ドキドキしながらトレーニングマシンのエリアを覗く。しかし、玉置浩二と青田典子らしき人物の姿は見えない。間に合わなかったか。いや、落胆するのはまだ早い。ロッカールームにいる可能性もある。帰り際に一目見ることができれば、それで充分だ。
キョロキョロする私に、連絡をくれたバイト仲間が手招きしている。私は乳酸の溜まった足をふらつかせながら、吸い寄せられるようにそちらへ向かった。バイト仲間が、「これ……」と指をさす。私は息を飲んだ。受付の隅で、二人が返却したレンタルシューズがアベックで私を待っていた。
時は流れ、大学を卒業した私は実家を出て札幌で働き始めた。「作りそこねた落とし穴」というのは、私のようにいつしか出て行ってしまう人が多いということを意味しているのかもしれない。
すすきので飲むようになると、時折、玉置浩二の噂を耳にした。すすきのでの目撃談は多いらしく、スナックに玉置浩二が突然入ってきて自分の歌を一曲歌って去って行った、なんて話も聞いた。普通なら信じ難い話であるが、私はそれを聞いて、あり得るかも、と思った。というのも以前、玉置浩二がバラエティ番組に出演しているのをたまたま見かけた時、玉置浩二はトークの合間の何気ないタイミングでギターを取り出し、さらっと「田園」を弾き語った。他の出演者が「こんな感じで歌ってもらっちゃっていいんですか!?」と恐縮すると、玉置浩二は笑って言ったのだ。
「歌なんて気軽だよ。」
その一言が、私の中にずっと残っている。プロとしての矜持を大切にする歌手も勿論かっこいい。しかし、日本屈指のボーカリストが、ただ好きだから歌っているということに、その時の私は妙に感激してしまったのであった。
そして2015年、夏。私はライジングサンロックフェスティバルの会場を走っていた。レッドスターフィールドのザ・クロマニヨンズを少しだけ見た後、一番大きなメインステージであるサンステージに向かって走っていた。目的はこのあと出演する安全地帯である。前々から玉置浩二の歌声を生で聴いてみたいと思っていたので、ライジングサンへの出演が発表された時には嬉しくて思わず声をあげてしまうほどだった。こればかりは一分たりとも遅れるわけにはいかない。ライジングサンの会場は広い。広くて足元が悪い。ゆっくり歩けば20分以上かかる道のりだ。私はあの日と同じように、気持ちを高ぶらせながら走った。荒野みたいな道のりを、スニーカーを砂まみれにしながら走った。
急いだ甲斐あって、少し早くサンステージに到着した。大勢集まった観客の隙間を縫って出来るだけ前方へと進む。もうすぐ、玉置浩二に会える。歌声が聞ける。そう思うとわくわくが止まらなかった。
しばらくするとスクリーンにアーティスト名が紹介され、安全地帯のステージが始まった。会場のボルテージが一気に高まる中、まずステージに登場したのはDJであった。DJ……? と一瞬思ったが、EDMっぽくアレンジされた安全地帯の曲が流れると、観客はフゥゥゥゥ!!!!と盛り上がった。80年代から活躍するベテランだというのに、このような今っぽい演出も取り入れているとは流石である。その心意気にこちらも応えねばなるまい。私は安全地帯mixに合わせて、ノリノリで体を揺らした。
しかし、まさかの事態が起こった。メンバーが出て来ない。10分経っても、メンバーが出て来ないのである。フェスというのは持ち時間が決まっているため、アーティストは大抵すぐに出て来る。しかし、出て来ない。安全地帯が出て来ない。不穏な空気が漂い始める。DJが曲を繋ぐ度、最初の方はフゥゥゥゥ!!!!だった歓声が、心なしかフゥゥゥゥ!?!?という感じになっている。期待と不安が入り混じっている。体を揺らしつつスマホで「安全地帯 DJ」と検索してみたが、安全地帯にDJが加入したという情報はない。じゃあ、誰。安全地帯のステージでかれこれ10分以上一人でDJプレイをしているこの人は、誰。そんな気持ちが最高潮に達した頃、ステージの脇から満を持して登場したのは安全地帯! かと思って歓声を上げた観客の前に現れたのは、黒の衣装に黒のキャップを被った二人の女性ダンサー。誰。またしても、誰。念のため「安全地帯 ダンサー」で検索してみたが、やはり情報はない。安全地帯mixに合わせて妖艶なダンスを踊るダンサーの二人。このダンスタイムが更に数分続き、まさか出て来ないのでは、という不安を抱き始めた頃、ついにメンバーがステージに現れた。良かったこれで一安心、かと思いきや、出て来ない。そう、玉置浩二だけ出て来ない。DJ、ダンス、バンド演奏だけが続く。自分はなぜ体を揺らしているのか、何が何だかよくわからなくなってきた、その時だった。
ついに、ついに玉置浩二がステージに現れた。登場まで15分以上。そして歌い始めた曲は「じれったい」。未だかつてこんなにもじれったい「じれったい」があっただろうか。本当にじれったい。そして上手い。歌が上手い、上手過ぎる。まるでオーケストラのような重厚感。その歌声を聴いた瞬間、全ての感情が攫われた。誰、とか出て来ない、とか一瞬で全部忘れた。只々、感動だけがそこにあった。
続いて玉置浩二は「悲しみにさよなら」をしっとりと歌い上げた。全身を包み込まれるような、温かい歌声に酔いしれた。ふわふわと名曲の余韻に浸っていると、信じられないことにステージ上では何やらもう終わるような気配である。そんなまさかと驚いていると、玉置浩二がダンサーの女性二人を「20年振りにC.C.ガールズ再結成!」と紹介した。なんと、踊っていたのは妻の青田典子(と藤原理恵)だったのである。私の5年越しの願いが叶ったのだ。私はついに、アベックをこの目で見たのである。心の中にずっと残っていた二足のレンタルシューズが、笑顔で手を振る二人の姿へと昇華された。
その後、全員が袖にはけて行き、まさかの二曲に観客はどよめいた。しかし、玉置浩二だけがアコースティックギター片手に戻って来て、そこからは手前のお立ち台でオンステージ。「田園」を弾き語り、マイクを置いて「夏の終りのハーモニー」をアカペラで歌った。涙が出るほど素晴らしかった。四曲を歌い、満面の笑みを浮かべながら手を振り去っていく玉置浩二。凄かった。怒涛のステージだった。あの歌声の前では、あらゆる常識が吹き飛ばされてしまう。私はこのステージのことを、一生忘れないだろう。
このご時世で実家にも気軽に帰れない日々が続いている。いつになったらまたフェスやライブを思う存分楽しめるようになるのか、まだまだ予想のつかない状況だ。
でも、いつか普通の日常が戻ってきたら、またあの歌声を聴きに行きたいと思っている。できれば今度は、故郷の旭川で聴いてみたい。作りそこねた落とし穴の中で、私のできそこないの部分を、玉置浩二の歌声が力強く包み込んでくれるに違いない。
(サムネデザイン:コスモオナン)