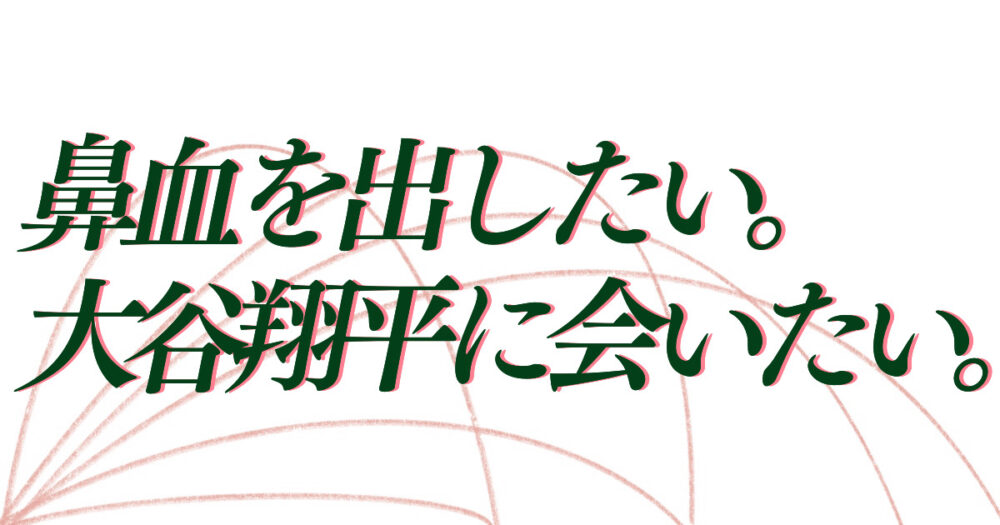剥き出しの闘争心と抜群に低い運動神経を持ち合わせた私の顔面にバスケットボールが直撃したのは高校時代、体育の授業でのことであった。
二組に分かれ行われたバスケのゲーム。私は全力でコート内を走り回っていた。自分としては目にも止まらぬ速さで駆け抜けているつもりだが、実際は50メートル走11秒台の人間の動きでしかなく、これは寺田心くん小学三年生時のタイムとほぼ同等であり、見よう見真似でレイアップシュートを繰り出すも、そのフォームはほとんどおっぱっぴーであった。しかし、それでも私の心の炎が消えることはなかった。自分はもっと出来る、そう信じていた。あのころ私が好んで飲んでいたパックのイチゴミルクには松岡修造の爪の垢が混入していた可能性がある。私は走った。自分を信じて走り続けた。そして味方からのパスを受け損ね、顔面にボールがピーヤした。
衝撃は凄まじく、漫画のように星が飛び出したのが見えた。私はその場にへたり込み、両手で鼻を押さえて俯いた。心配したクラスメイトたちが周囲を取り囲む。痛い。ものすごく痛い。しかしその激痛の中に、一筋の希望の光が射していた。
鼻血が出たかもしれない。
これは出た。絶対に出た。こんなに痛いのだから、出たに決まっている。ズキズキ痛む鼻。ワクワク高鳴る胸。ついにこの時が来た。激痛と引き換えに、長年の願いが叶うのだ。
私は生まれてこの方、鼻血を出したことがなかったのである。
幼少期、周りの子たちは事あるごとに鼻血を出した。ぶつけたり転んだりほじったり、時には何も無くとも出した。だから私もそのうち出るだろうと信じていたのだが、待てど暮らせど出ない。私だって子どもらしくぶつけたり転んだりほじったりして過ごしているのに何故なのか。母に聞けば、「鼻の粘膜が強いんだね」と言う。鼻の粘膜が強い子を産んだという自負なのか、どこか誇らしげだった。確かに鼻血が出やすくて困っている人もいるだろうし、喜ぶべきことなのかもしれない。しかし一度たりとも出ないなんて、さすがに頑丈過ぎやしないか。私の鼻の粘膜は超合金製か何かなのか。
誰かが鼻血を出すと、教室は騒めく。止まる授業、心配する先生、ティッシュを求め飛び交う声、駆り出される保健係。日常を脅かすことのない適度なパニックがそこにはある。鼻の穴にティッシュを詰め込んだ、あの風貌もいい。マヌケで、ワイルドで、ポップ。皆が少女漫画を読んで「私の初恋はいつかしら」と夢見たように、私はギャグ漫画を読んで「私の鼻血ブーはいつかしら」と夢見たものである。
「鼻血が出る感覚って、鼻水とは違うの?」
そう尋ねると、みんな口を揃えて言う。
「全然違うよ! 鼻血なら絶対に“わかる”よ!」
私も違いがわかる女になりたい。ダバダ~ダバダ~で、ダバダバ鼻血を出したい。
そんな切なる願いを胸に抱き続け高校生となった私に、千載一遇の鼻血チャンスが舞い込んだわけである。バスケットボールは鼻にクリーンヒットした。衝撃は申し分ないはず。体育館の床に膝を付き、俯いたまま祈った。どうか鼻血が出ていますように。さっき飛び出た星に願いを。ゼペット母さんがくれたこの沈黙の鼻にどうか命を吹き込んでください。これからの人生、正直に生きていきますから。嘘をついたら鼻を伸ばしてもらって構いませんから。
私は期待を胸に、鼻を抑えていた手をゆっくりと離した。しかし、そこに鼻血らしきものはなかった。そんな、まさか。周囲を見回してみるが、飛び散った鮮血などは見当たらず、ただ床の木目が広がっているだけであった。こんなに、こんなに痛いのに、あんまりだ。両目からポロポロと涙が溢れた。クラスメイトが「大丈夫? 痛い?」と私の顔を覗き込む。「うん、痛い。すごく痛い。」私は嘘をついた。それは痛みの涙ではなく、悔し涙だった。鼻は伸びなかったけれど、少しだけ腫れた。
その日を境に、私は鼻血について考えることをやめた。あの激痛をもってしても出ないのであれば、もう諦めるしかない。忘れよう。忘れて、楽になろう。そう思った。鼻血への憧れはあの日の絶望と共に心の奥底へと押し込められた。それからは鼻血のことは忘れて過ごした。平穏な日々だった。しかし時折、目を覚ますと何故か泣いている、そんな朝もあった。何の夢を見ていたのだろう。いつも思い出せないが、そんな日は決まって目玉焼きにケチャップをかけたくなった。真っ赤なケチャップを見ているうちに「ウッ……!頭が……!」的なこともあった。文房具屋で赤ペンを買おうとして「あいうえお」と試し書きするつもりが何故か「ネスカフェゴールドブレンド」と書いていたこともあった。時は流れ、気付けばアラサー。結婚もして、穏やかな日々が続いていた。
そして先日、夫が鼻血を出した。特に前触れもなく、自然に出てきたようだった。夫は慌てず騒がず、上を向いてティッシュで拭った。誰かが目の前で鼻血を出すのを見るのは久しぶりだった。
「鼻血が出る感覚って、鼻水とは違うの?」
懐かしい質問が口をついて出て、ハッとした。鼓動が高まる。鼻つっぺをした夫が、こちらを振り返る。熊川哲也の如くしなやかに、大沢たかおのような色気を纏い、唐沢寿明のような熱い眼差しで、和泉元彌の如くそろりそろり近づいて来る。
「全然違うよ! 鼻血なら絶対に“わかる”よ!」
ダバダ~~~ダバダ~~~ア~~~~~~(ドリカムver.)
私は思い出した。あの日の絶望を。いや、それを上回る、憧れという名の希望を。忘れたはずの想いが、胸の奥底からドクドク脈を打つように溢れて来る。
鼻血を出したい。やっぱり出したい。
そういうわけで、私は理想の鼻血の出し方を考えることにした。せっかく出すなら一生の思い出になるような、ド派手な出し方をしたいものである。
バスケットボール顔面直撃もなかなか絵になるシチュエーションではあったが、如何せん私の超合金製の鼻はびくともしなかった。となると、衝撃だけでは足りないのかもしれない。鼻血の三大原因といえば、衝撃、興奮、チョコレート。ならば、チョコレートを摂取し、興奮した状態を保ちながら、衝撃を与える、というのはどうだろう。三つの条件を高水準で満たしたとき、私の鼻の粘膜をぶち破ることができるのではないだろうか。
しかし、そうなると一番の問題は「興奮」である。ウブな若者ならまだしも、こちとら経験豊富なアラサーの既婚者。ちょっとやそっとで大興奮するほどヤワではない。
しばらく考えた結果、私は一つの答えを導き出した。今、私を爆発的に興奮させることができる唯一の存在。それは、大谷翔平である。
メジャーリーグ、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平。野球に興味がなくとも、この名を知らない日本人は最早いないであろう。メジャーリーグで投手と野手の二刀流をやってのける漫画以上に漫画みたいな異次元の天才、大谷翔平。
今年の大谷は絶好調である。ホームランが現在32本でメジャー単独トップ。本当に毎日のように打っており、最近は毎朝大谷のホームランを見ることが日課になっている。打った瞬間ホームランだと確信し、歩きながら飛んでいくボールを見届ける「確信歩き」の格好いいこと。不安の多いご時世でいつもどこか鬱屈した気持ちを抱える中、海の向こうで豪快なホームランを放つ大谷の姿を見ると何だか胸がすっとする。ビッグフライ太田胃散。ありがとう、いいくすりです。
そんな大谷翔平が同じ北海道にいたなんて、今となっては何だかもう信じられない話である。北海道日本ハムファイターズ時代、私は何度も札幌ドームへ観戦に行き、大谷のプレーを直接この目で見た。今より少しだけ、身近な存在だったのである。同じく日ハムファンである母親は大谷のことを「うちの翔平」と呼び、当時まだ独身だった私に「翔平があんたのお婿さんになってくれたらねえ……」などと言ってうっとり目を輝かせていたが、大谷は夢を叶えるため、私と栗山監督を残しアメリカへと旅立った。もし、メジャーリーガーとなった大谷に再会できたなら、これ以上の興奮はない。更には目の前でホームランなど放ってくれようものなら、この沈黙の鼻も火を噴くこと間違いなしである。
さて、記念すべき初めての鼻血。せっかく出すならより景色のいい場所で出したい。大谷のホームランが見られる場所で、より景色のいい場所と言えば、そう、エンゼルスの本拠地であるエンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムのセンター後方にある岩山である。この岩山はディズニーランドのビッグサンダー・マウンテンを模したもので、元祖ディズニーランドの街、アナハイムならではのモニュメントである。この岩山の上に立って、大谷のホームランを見たい。ディズニーランドに行ったことがない私にとっては有名アトラクションの雰囲気も味わえて一石二鳥である。
確実に鼻血を出すためには、大谷がホームランを放ち私の興奮がMAXに達するその瞬間、鼻に強力な衝撃を与える必要がある。となれば答えは一つだ。ホームランを顔面に受ける。これしかない。大谷はよくあの岩山のところにホームランをぶち込んでいるので期待できるはずだ。衝撃のあまりエンジェルたちと共に昇天しそうになるかもしれないがそこは胆力でグッと堪えるとして、もう一つ忘れてはならないのがチョコレートである。これに関しては岩山に陣取った段階であらかじめ大谷の大好物であるコンビニの細長いチョコクレープを大谷が高校時代に書いた目標達成シートのマス目の数だけ食べておく(81個)。これで完璧。興奮、衝撃、チョコレートの三つの条件が揃い、私の超合金製鼻粘膜も撃破されること間違いなしである。確信歩きならぬ確信鼻血。岩山の上、エンゼルスのユニフォーム姿で仁王立ちしながら鼻血を垂らす私の堂々たる姿を想像してほしい。これぞ初めてに相応しい、最高の鼻血ブーである。例えユニフォームに鮮血が飛び散ったとしても心配はいらない。エンゼルスのチームカラーは情熱の赤だ。
これを書いている間に大谷はまたホームランを打ち、ホームラン数は33本となった。それでいて投手としてもチームトップの防御率を誇っているのだから、本当に夢みたいな野球選手である。「夢を与える」という言葉があるが、大谷翔平は正に、人々に夢を与える存在と言える。だが恐らく大谷は誰かに夢を与えるために野球をしているわけではない。今、大谷自身が夢の真っ只中にいて、夢を叶えている最中なのだ。そんな大谷を応援することで、私たちは夢を与えられている。
何十年後、年老いた私はきっと大谷の現役時代をリアルタイムで見ていたことを孫に自慢するだろう。しかし、それだけでいいのだろうか。大谷がメジャーでホームランをバカスカ打っていた頃、私は何をしていたのか。それを語れるような人生を歩んでこそ、大谷と同じ時代を生きたと胸を張って言えるのではないだろうか。大谷に鼻血を出してもらおうとするのではなく、私も自分で、自分の力で、鼻の穴に指を突っ込むべきなのかもしれない。何度でも何度でも、突っ込んでみるべきなのかもしれない。10000回だめでへとへとになっても、10001回目は何か変わるかもしれない。10000回だめで望みなくなっても、10001回目は、出る。
鼻血は自分で出すとして、大谷に会いたい気持ちは変わらない。コロナ禍でまだ行けていない新婚旅行の行き先をロサンゼルスにすることを私は密かに狙っている。高校卒業後すぐメジャーに挑戦するつもりだった大谷に入団を決意させた日本ハムファイターズ伝説のプレゼン資料「大谷翔平君、夢への道しるべ」に習い、私もプレゼン資料「新婚旅行、ロス行くべ」を作成し、夫を説得するつもりである。
この時代に生まれ、大谷という天才の目撃者になれる喜びを噛み締めながら、私も自分の人生を全力で生きる。そして、いつか大谷に会いに行けるその日まで、日本から声援を送り続けよう。跳べ、大谷!夢の向こう側へ!